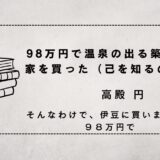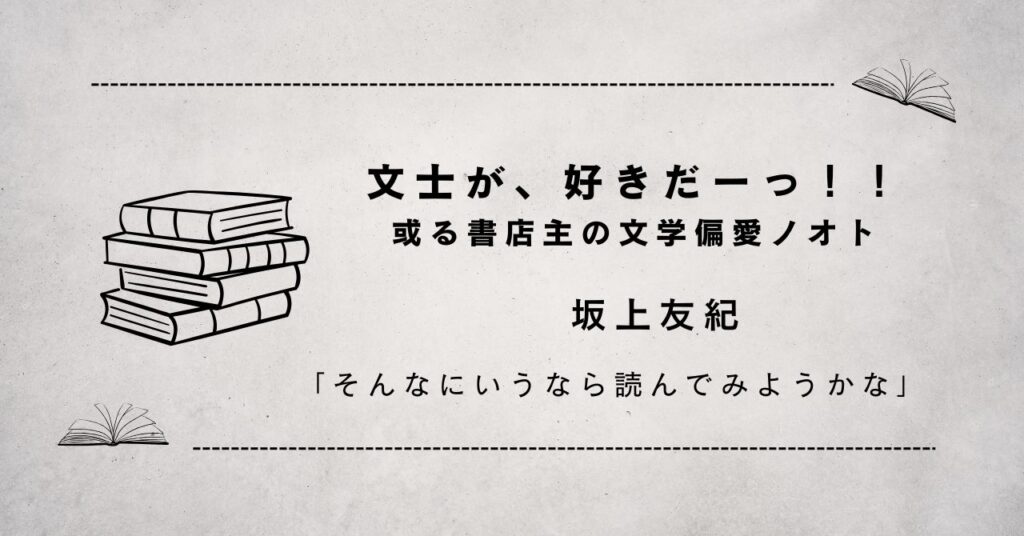
この本を読んだきっかけは、もともと「本は人生のおやつです!!」が好きであり、その店主さんの著書ということで「あの口調で書かれる本なのかな?」と興味深々だったから。ただ、私は文士を知らない。大正・昭和の文士といえば、高校時代に国語便覧でみたか、国語の教科書に載っていたのを読んだぐらい。
正直、坂上さんの本じゃなければ手に取っていたかわからない。(多分、とってない)どうしても、教科書に載っている人の作品は「すごい作品」な感じがしてハードルが高い。国語のテストにも出ていたことがあるので「読めなかったら、理解できなかったらバツが付くような不安」がぬぐえない・・・。そしてそもそも難しい。
そんな不安を乗り越えて、このかわいらしい書影の本を購入しました。
それでも生きていく文学
井伏鱒二の山椒魚。これは、呪文のように覚えている著者と作品名。でも、どんな話か全く知らなかった。どうやら、岩屋から出られなくなった山椒魚が、岩屋にまぎれこんできた蛙を前に、同じ目にあわせてやるーと自分の体で入り口をふさいで意地悪をした話。特に二匹が岩屋から出られたわけでもなく、ハッピーエンドでもなく淡々とその過程がかかれているだけ。
で、どうなん?と言いたくなるけれど、考えてみれば日々の生活ってそういうこと。特別なことはないけれど、そういうものっていうか「それでも生きていく」というのが、私にはものすごくスッとはいってきた。
だって、今の我が家の状態はまさに「それでも生きていく」状態。お写真をみてもなんというか、どーんといてくれる安心感というか王道感を感じてなんかわからないけど大丈夫って感じがした。
乙女、変態、生活
「乙女子の犀星」「覗き見の犀星」って、なんというふたつ名・・・。これは坂上さんがつけられたのかな?
そして「生活の犀星」。たとえ生活苦のただなかにあったとしても、「なにくそ!」と踏んばりぬけるようなハングリー精神が彼のなかにあるのだ!
どうやら犀星には見た目のコンプレックスがあったそうです。お友達がイケメンだったのでなおさらそう思ったのかもしれないとのこと。(そのお友達というのは芥川龍之介や萩原朔太郎)芥川龍之介は教科書か国語便覧かでよくみたからすぐに思い出せる。うん、イケメンだ。
自分の姿に自信がないから「近づく」のではなく「覗く」ようです。そして覗き見たからいろいろと妄想してしまって、その結晶として素晴らしい表現がでていったのか・・・とのこと。
妄想万歳
満たされないことが多く、不満があり、飢餓感があって、その鬱屈したものが昇華しての犀星の文学・・・。
文士、そこまで自分を削るのか・・・。
私は室生犀星が一番気になったかなー。だから「杏っ子」は気になる。
杏っ子の終わりの方で
「その意気で居れ、後はおれが引き受ける。不幸なんてものはお天気次第でどうにでもなるよ。人間は一生不幸であってたまるものか。」
これがすごく好き。だって、できる出来ない関係なく「なにくそ」ってなるときあるもん。一生不幸であってたまるもんか!ほんとにね!!!
感動に理論は必要ない
神西清はとても優秀なアドバイザーであり、翻訳者。たくさんの資料をあつめて小説を書く準備も整っていたのに、多才すぎて時間が全く足りなかった人。なイメージ。
建築家を志望していたけれど、フランス文学熱中しにフランス語を独学。そしてロシア語も。多分、英語とかもできたんだろうなー。すごいよね。翻訳がとても有名らしい。ちなみに私は聞いたこともない。
そんなスーパーエリートのような人が、「感動に理論は必要ない」って言ったのに驚いた。感動もすべて言語化して説明できるような人だと思ったから。「なんかわからんけどすごい」っていうのもOKなんだ。(そういうことだよね)ホッとするよね。
五月のそよ風をゼリーにして持ってきて下さい
私は詩が苦手。どうしても「で、どうなん?」と思ってしまうし、抽象的過ぎてわからなかったりカッコいい言葉すぎてついていけなかったり。だから手に取ろうと思ったこともない。
でも、立原道造は違った。引用してあった詩「夢みたものは・・・」は、読むと情景が目に浮かぶ。とにかくわかりやすい。結核で24歳という若さで亡くなられていますが、東大卒で建築家。文学じゃないんだ・・・。
「そよ風をゼリーにして・・・」というのは、入院中の立原道造のもとへお見舞いにやってきた若林つやが「何か欲しいものは?」と尋ねたときの言葉。
読んだだけで、どんなゼリーか想像できてしまうような表現。詩ってこんなにストレートにくるんだーと驚きました。とはいえ、私はこの本に引用してあるものしか知りませんが・・・。
この本に出てくる6人の文士だけでも、関係性がある。誰と誰が親しくて、どんなことをしていて等々。関係性を知っていくと興味も出てくる。他にも多くの文士がいるけれど、私にはまずはここの6人を少しずつ知っていきたいな。
おわりに
「はじめに」に、坂上さんも書かれているのですが「むかしに書かれたというだけで、なんだか小難しそうな気がしていたよ。でもそんなことは全然なかったです。もちろん、作家によりけりで小難しい文章のひともいましたが、いっそフレンドリーといいたい文章のひとも結構いる!」とのこと。坂上さんも、小難しそうな気がしてたんだと驚きました。
この本を読んですぐに「さあ読むぞ!」といきたいのですが、やはり読みなれない時代、読みなれない文体で腰が引ける・・・。文学に詳しい友人に聞いてみると「岩波ジュニアとかで読んでみるとわかりやすいんじゃない?」ということなので、近代文学関係を探してみようと思います。
そういえば、文フリ京都で「百年の孤独」を代わりに読むの友田とんさんが「名著と言われるものって、すごそうに感じてしまうけど、結構くだらないことが書いてあるから気軽に読んだらいいよー」と言われていました。そういうことなのかもしれない。
気にはなっていたけど手が出なかった国語の授業で見てきた作品。いきなり本丸は無理なので、まずは外堀を埋めていこうと思う。