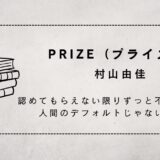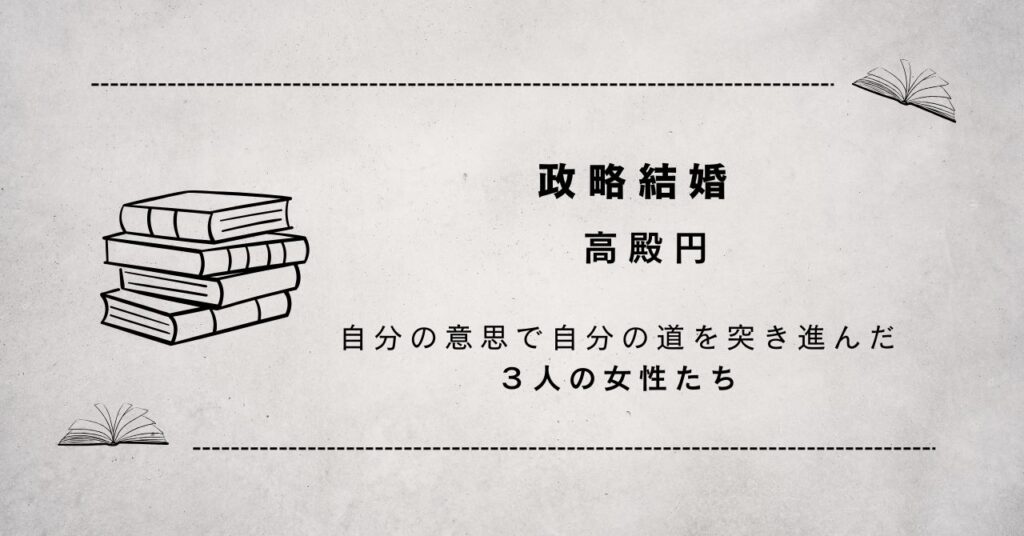
この本を手に取ったのは、高殿円さんの本だったことが大きい。以前に読んだ「コスメの王様」は「本を読みたい」という気持ちを思い出させてくれた本だったから。他にも色々気になる本があるのに、なぜ政略結婚だったかというと時代別の3人の女性たちのそれぞれの物語であり不思議な縁で繋がっているお話だったから。単行本の素敵な書影にも惹かれた一冊。3人娘のかわいい表紙。
平成のお家騒動(私の場合)
結婚ってどうしても自分1人の事情で決められないこともあった。
もう今は違うのかもしれないけれど、私は自分の結婚の時に「無理かもしれない」と何度も思った。結婚してから何年も経って母が教えてくれたんだけど、祖父母は私の結婚に大反対だった。もう、「勘当!」というくらいに大激怒だったらしい。「歓迎されてないだろうな」と思っていたけれどやっぱりそうだった。
それを母は親族たちに事情を話し、祖父を説得してくれるよう頼みまわってくれたらしい。幸い、親族は賛成してくれていたので皆さん協力して祖父を説得してくれ、なんとか結婚式当日まで自宅にいて、送り出してもらえた。
結婚式は車で2時間ちょっとかかるホテルだったので、できれば前日から泊まりたかった。夫家族は前日から泊まっていたので本当にうらやましかった。
我が家では、結婚式当日は見送られて出て行くのが筋ということだった。祖父は羽織袴で近所の人に恥ずかしくないようにということで、驚くほどビシッとして送り出してくれた。
朝5時に出たから、本家とお隣の親戚筋の方のみだったけど・・・。そんな朝早くからきてくれて本当に驚くやらありがたいやら。でも、今思えば、良かったんだと思う。儀式というか区切りをきちっとつけるのは人生の節目にあってもいいものかもだと思えたから。
お家の一大事というのはまだまだ平成でも続いていた。祖父の大激怒の理由というのが「家がなくなる」ことだったから。私が一人っ子なのに嫁に出てしまうということは、家がなくなるということだから。
私の両親も色々考えたと思う。それでも、気持ちよく送り出してくれた。どうやら、知り合いで長男長女の結婚を反対してなしにされたそうだけど、長女はその後結婚されなかったそう。それをみて親は「娘に結婚だけはしてほしい」と思ったらしい。
多分、私の両親は当時では珍しい部類だったと思う。でも、結婚までは、田舎の長男の跡取りとして育てられた。ただ「結婚」だけは「本人の意思」に委ねてくれた。多分、両親は多くの辛い別れをみてきたのだろうと思う。
自分が死なぬのはまだここですることがあるからなのだ(江戸末期)
生き残ってしまったから「自分がすべきこと」を必死で探してしまうと思う。生きていていい理由を。
生きていないと何もできない。
わかっていても、生きている限り何かに追い立てられてしまうかもしれない。
私はまだ取り残されたと感じる別れはしていない。それでも、今、まともに働くこともできず、自宅で家族の世話を中心に生きていると「何のために生きているんだろう」と思うことはよくある。
私も、私が産んだ子供たちも、社会に対してできることがあるんだろうか、お荷物と言われながら生き続けるんだろうか。だからこそ「自分がすべきこと」を無意識のうちに探しているのかもしれない。
そして、それをする理由も。
だけどタカさんは生きてるじゃない(明治大正)
「生きていること」を特別なことだと考えていなかった時がある。
それでも、結婚して家族が増えるごとに、生きていることの重みを感じるようになった。
タカさんは多くのことを飲み込んで生きてきたんだろう。今の時代から見ると、憧れるような生き方だけど、当時だとそうではないはず。それどころか後ろ指をさされるような・・・。
「生きてるじゃない」は一言だけど、大きな大きな一言に感じた。
そんな万里子さんも素敵だ。
血筋をたやしても何の罪にもならない時代がやってきた(昭和)
多くの家がそうなってきた時代だと思う。
それでも、まだまだそうは言い切れないお家もあると思う。
私の両親は、家に大正生まれの人がいる家といない家で考え方が大きく違うと言っていた。私も夫も大正生まれの祖父母と同居していた。だから結構、価値観は似ている。
そして、私の祖母は100歳でまだ健在だ。今でも「男は○○でないとあかん」とか言っている。そんな祖母は、そんな時代だったはずなのに、珍しく祖父を思いっきり尻にひいていた。もしかしたら祖父はめちゃくちゃ今どきの人だったのか!?
しきたりについては厳しかったけど、日常生活は祖母の横暴を適当にあしらっててそれはそれですごかった。
おわりに
- 選択の余地などなく嫁いだ家を懸命に守り通した勇。
- 家を捨てることなく自分の意思で進む道を選び取った万里子。
- 長い歴史のある公家伯爵家の血を、率先して絶やしたと語る花音子。
それぞれ、素敵な女性たち。そんな女性たちをつなぐ「九谷の皿」。
九谷焼を見てみたいって思ったし、そんなふうに受け継がれていく「もの」に憧れる。
ものを持たない時代とか、断捨離とか、すっきりと暮らして行くのがよしとされるし、あれもこれも置いておく場所もない。(実家には座敷蔵があって、祖母のお姑さんの嫁入りの時に持ってきた長持がまだあるらしいけど・・・)
それでも、何か「これ」という大事なものを大切にしたい。その「もの」には多くのものが宿っている気がするから。それはいいことだけでなく、戒めになるようなことも、辛いことも、たくさんあるだろうけど、それが続いて行くことなんじゃないかな。
家族でもなく血のつながりもない、周りの人との関係性、人と人との距離感についても考えさせられる
ここに関しては、ちょうどプライズを読んだ後なので、ぐさっときた。これは解説に書いてあったことなのだけど、「人と人との距離感」いつの時代も大切なことなんですね。

今の自分の立ち位置に迷いが出た方にぜひ。